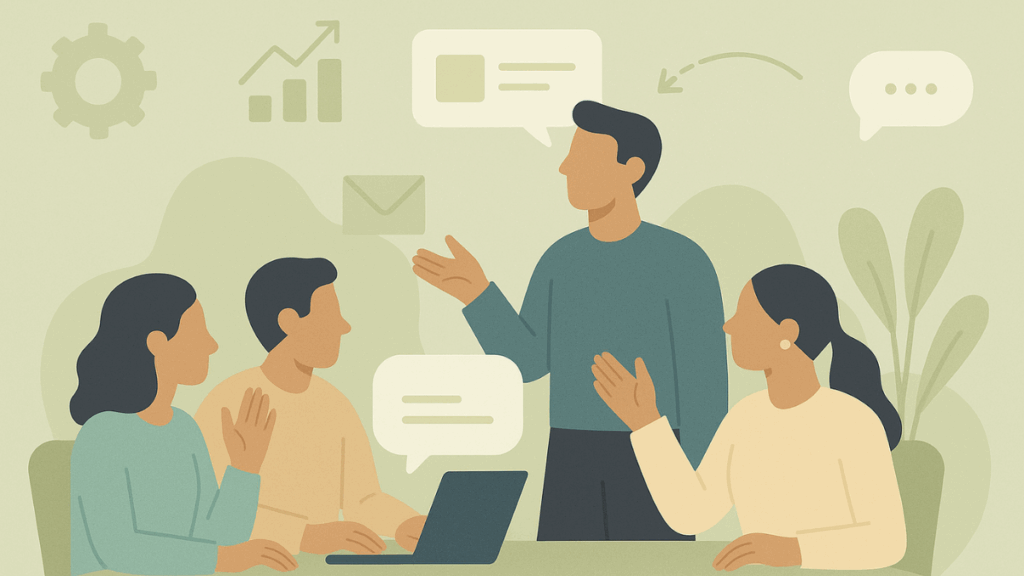
結論:情報分散のコスト課題から段階的に浸透
私が30人規模のスタートアップでNotion導入をリードした際に意識したのは、「課題を定量的に示して説得 → 社内決裁 → 全社浸透 → AI拡張」という流れです。
最初から理想を追求するのではなく、理想から逆算してシンプルに「情報の一元化」から始めたことで、Notion導入からレベルの高い使い方へとスムーズに進みました。
Notionを社内で導入するか迷われている方、導入したがあまりうまく浸透していない方の参考になれば幸いです。
ステップ1:課題と導入目的の整理
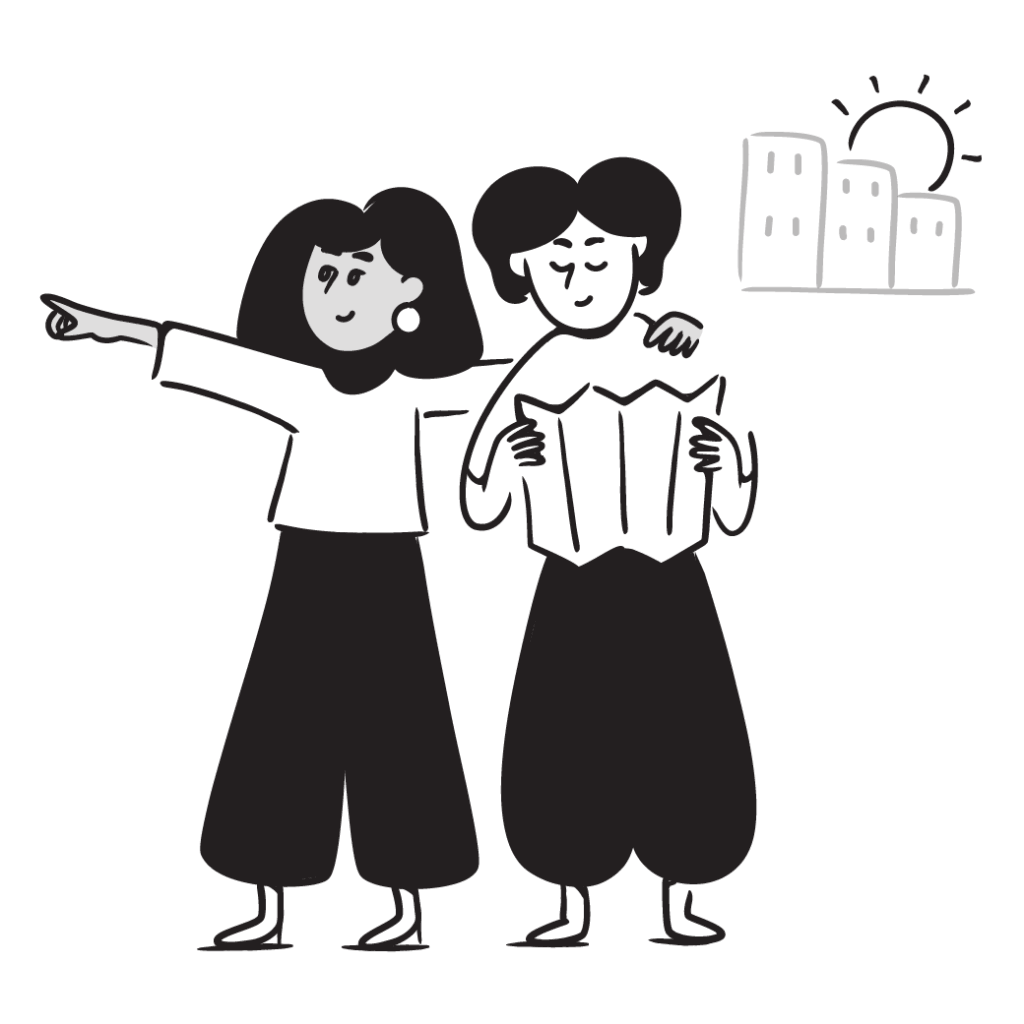
課題はシンプルに「情報が資産になっていない」ことでした。
- チームごとバラバラな議事録フォーマット
- 様々なツール(スプシ、ドキュメント、Word、Excel、Figma、メモ等)で管理されるドキュメントたち
- 自分が知らないところで何が起きているのかわからない情報たち
「情報のサイロ化」というやつです。
自分のチーム以外、自分が参加したミーティング以外の情報がほぼ入ってこない。情報を手に入れるには当事者に聞きに行くか、埋もれている情報を探すかのどちらか。
「そんなことをしているなら仕事しろ」と言われそうですが、実際各人が持っている情報レベルがチグハグなため、会話が毎回前提から入るので長いミーティングになったり、アイデアや施策がチーム間でバラバラで出戻りが多かったり、Slackのスレッドが毎回長くなって非同期コミュニケーションのメリットが失われていたりと、「情報が資産になっていないことによる無駄」が多発していました。
これが今回Notion導入によって解決したかった課題です。
コラム:Notionはクレカ払い
Notionの支払い方法は、基本的にクレジットカード払いとなります。
そのため企業によっては、社内ルールによってクレジットカードの扱いや利用方法が複雑で、導入までに時間がかかってしまうケースもあるでしょう。
ひとつ救いとしては、一度クレジットカードで決済ができればその後は必要ないことです。登録後は月額または年額で自動的に引き落とされ、利用人数の増減はWeb上で行えてクレジットカード情報の更新は必要ないので、導入タイミングでクレジットカードさえ登録できればその後はクレジットカードがなくても問題ないでしょう。
ステップ2:レクチャー会とワークショップ形式で浸透

無事に社内決裁され、クレジットカードで決済ができたら、全社導入に合わせてレクチャー会を実施しました。内容は以下の通りです。
- Notion導入の背景と目的を共有
- 基本操作をNotion上で資料を作って解説
- その場で触ってみるワークショップを開催
背景と目的は、ステップ1で整理したものなので、新しく考える必要はないですが、できるだけ自分ごと化して利用してもらえるように、現状の不便不満とNotion導入による解決は伝えたほうがいいでしょう。
2時間のレクチャー会兼ワークショップという形式を取ったのは、導入初期のファーストインプレッションで如何にわかりやすさ、使いやすさを感じてもらうかが重要だと考えていたためです。
人の印象は出会って3秒で決まると言われるように、使い方がわからないからという理由だけでNotionの印象が下がってしまうのは避けたかったので、レクチャーしつつも実際に手を動かして、この会が終わることにはそれぞれが利用し始められる状態にしておきたかったから。
資料は簡単に以下を網羅しました。
- Notionを使い始めるまでの最初のステップ(アカウント登録やデスクトップアプリのインストールなど)
- Notionの画面構成について(サイドバー、設定画面、プライベートやチームスペースのフォルダ等)
- Notionのページでどんなことができるか機能について(ドキュメントの書き方、パーツ、データベースなど)
ここでのポイントは、詳しくやりすぎないこと。ざっとこんなことができるイメージを持ってもらうことがこのあとに行うワークショップにつながってきます。
最後にワークショップ。ここでは実際にページを作成したり、ドキュメントを書いたり、データベースを作ってみたりして、Notionに触れてもらいます。
特に「プライベート」と「チームスペース」のフォルダを区別してドキュメントを作成することが前提として認識しておくことで、個人ではどう使おうか、チームではどう使おうかと想像できるようにしておくのがポイント。
また、機能の使い方を説明しすぎないのも自ら手を動かして試してもらい、私自身思いつかなかった利用方法を引き出すことにもなったので、ガッチガチに説明しすぎないアイデアが生まれる余白を作っておくのもおすすめです。
ステップ3:小さく始める

導入後、全社に展開する際は、まずアジェンダと議事録のデータベース化を第一歩にしました。
理由は、いきなり様々なドキュメントをNotionに移行するのは時間がかかりすぎますし、反発が出てしまう可能性もあったので、アジェンダと議事録は統一して整理・管理することを提案しました。
仕組みはいたってシンプルです。
- 会社のトップページにアジェンダ・議事録のマスターデータベースを作成する
- データベースのプロパティ「マルチセレクト」でチーム名を設定
- チームごとのチームスペースを作成する
- リンクドデータベースを各チームスペースに設置して、フィルターでチーム名を指定
これで会社トップページには全体のアジェンダ・議事録が管理され、チームスペースでは各チームのものが管理できます。
また以下のルールを最初に設定しました。
- 会議のアジェンダをNotionで作り、カレンダーにリンクを貼る
- 全社DBは編集禁止
- 外部資料はリンクにいれる
特にアジェンダを作成した際、カレンダーにNotionリンクを貼り付けるというルールは統一しました。
この仕組みによって「会議資料を探す=Notion」が当たり前になり、社内の認知と利用率が一気に高まったので、浸透に一役買っていたと思います。
簡単にデータベースのリンクをコピーできる活用方法は以下をご覧ください。
ステップ4:仲間を巻き込んで利用範囲を拡大

アジェンダ・議事録が定着すると、Notionに価値を見いだすメンバーが自然に増えていき、「こういうことをしたいんだけどどうしたらいい?」といった自発的で、アクティブな質問が来るようになってきました。
このタイミングで、そうした方々に対して以下のような使い方を提案していき、少しずつNotionの活用範囲を広げていきました。
- 個人タスク管理
- チームのタスクボード
- バックオフィス文書の集約
- 営業資料やの集約
- 開発案件のチケット管理
- プロダクトに対するフィードバック集約
- 顧客問い合わせの集約
私のチームだけでなく、他チームにもNotionの活用が広がっていき、情報が集約・整理されていくことで単なる「会議用ツール」から「全社の基盤」へと育っていきました。
ステップ5:ステップアップ!AIの活用
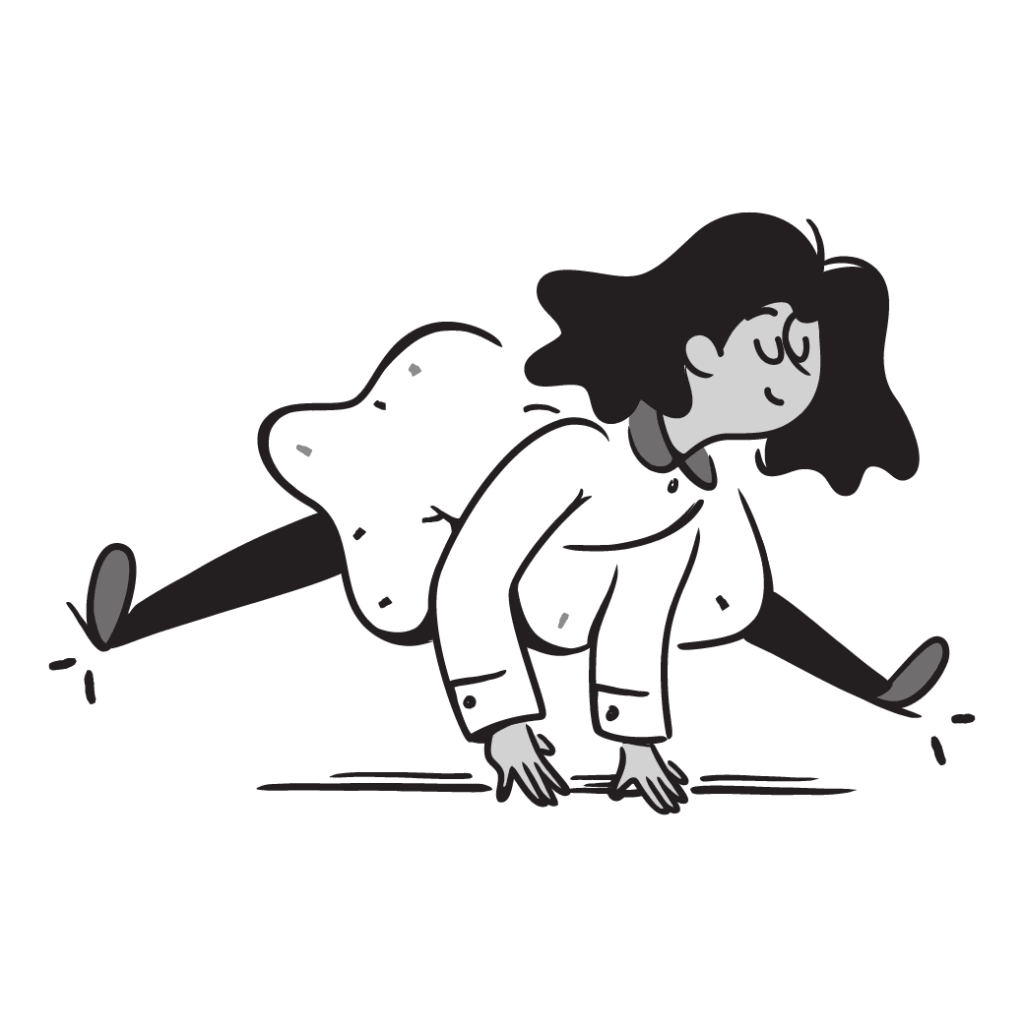
Notion導入から半年後、情報が十分に溜まっていき、各チームごとに整理がされ、「なにか知りたいときはNotionを見る」という認識が浸透したタイミングでAIの活用を進めました。
このタイミングで再度レクチャー会とワークショップを開催して、以下のことをポイントにさらにNotionの活用の幅を広げていくようにしました。
- Notion AIによる情報の探索
- メール文作成、施策案作成など文章のAI生成
- ミーティングの録音、文字起こし、議事録作成のAI自動化
- Notion上でのChatGPTなど他のLLMの活用
- Notion AIとChatGPTやClaudeなどのLLMとの違い
ここまで来るととてもスムーズにAIも使いこなせるメンバーが多く、様々なアイデアや改善に向けた動きが見られるようになっていきました。
Notion導入で実感したポイント
- まずは、誰もがわかりやすいところから小さく始めることで、入りがスムーズだった
- いきなり全員ではなく、少しずつ同士を広げていくことで自然と勢力を強めていける
- Notionにこだわるのではなく、解決したい課題とコスト感覚を意識することで生産性向上とコスト削減の本来の目的を見失わない
今後の目論見
Notionの枠を超えて、高速で事業の成長につながることを探し、試し、評価して、実行していける仕組みを作っていくことが今後やっていきたいことです。
マーケティングやシステム開発、営業、顧客サポートなど「チーム」や「職種」という枠組みや垣根を超えて仕事をしていくことが組織にとっても、人にとってもこれからのAI時代には必要だと思っています。
特に個人においては、自分の得意領域だけで仕事をしていたらAIを活用する人と比べてクリエイティブの質やスピード、創出する価値で劣ってしまい、市場価値や年収にも響いてくるでしょう。
そういった意味で、Notionを使うことが目的化するのではなく、MCP(Model Context Protocol)を使って様々なツール同士をつなぐことで、人ひとりが創出できる価値を最大化させていけないか模索していくことが今後の課題であり、目論見でもあります。
現状の考えでは、Notion、Obsidian、Cursor、Figmaをうまく使うことで個人かたチームまで高速にPDCAを回していけるのではと考えています。模索の目処が立ったら記事にしていきます。



